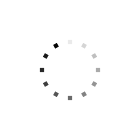日本と中国、子育ての違い
みなさん、初めまして。バルコニア上海の中嶋です。私は現在、中国上海で娘(3歳)、息子(10ヶ月)の二人の子育てをしています。
みなさん中国での子育てと聞いてどんな印象を持つでしょうか?同じアジアの国だし、文化や生活習慣も近いものがあるし、日本と中国ではそんなに大きな差はないんじゃないか?と感じるかもしれませんが、いざ子育てをしてみると色々な違いを感じることがあります。
そこで今回は、実際に感じた子育て、子供に対する日本と中国の違いをご紹介します。

子育ては6人体制
中国では祖父母が孫の面倒を見るのが一般的です。ですので、両親、祖父母(母方2名、父方2名)の6人の大人が育児に関わることになります。
同居して両親が仕事で家にいない日中にサポートしてもらっている家庭もあれば、子どもだけ祖父母の家に預けて両親は都市部で仕事に打ち込むという家庭も少なくありません。
中国は結婚、出産後も仕事を続ける女性が多いですし、子どもの教育費や家のローンなどにもコストがかかるため夫婦共働きである家庭がほとんどです。
経済が発展するにしたがって最近では専業主婦も増えていますが、それでもやはり祖父母からのサポートがあるのが一般的で、いわゆるワンオペ育児という言葉は中国で耳にすることはあまりありません。
また、中国では、安全面、教育面の安全性懸念から、子供の送り迎えが基本で、小学校は祖父母が毎日送り迎えをしています。弊社の前の学校も夕方3時〜4時頃になると祖父母と小学生であふれかえります。一般的に中国では小学生が一人で登下校することはありません。
その一方で、祖父母に任せてしまうと、甘やかしすぎてしまう傾向があり、自分自身で子どもを育てることにこだわる両親もいます。 また、高齢者の話すマンダリンのアクセントが子どもの言語習慣に影響を与えることもあり、マンダリンがちゃんと話せない子どもが増えているという問題も抱えています。
寒さは大敵、靴下履かせなさいおばさん
中国では中医学が生活の中に浸透していて、寒さは子どもにとっても大人にとっても大敵とされており、子供にはとにかく厚着をさせます。
そんな中国では生まれた頃から夏場でも靴下を履かせるのが一般的。日本ではよほど寒くない限り靴下は履かせません。むしろ赤ちゃんは体温調の観点から履かせない方が主流なっています(足や手から熱を発散しており、体温調整が苦手な赤ちゃんは靴下で覆ってしまうと熱が上がりすぎてしまう)。
同じ感覚で中国の街を歩いていると、きっと「靴下を履かせなさい!、風邪ひくよ!」と知らない人に声をかけられること間違いなしです(心配はありがたいのですが、突如靴下履かせなさいおばさんが出現します)。
子育ては祖父母も参加し、みんなで育てようという認識があります。そのため他人の子に対しても心配になりつい口を出してしまう様で、特に靴下には非常に厳しいです。。。
また、もうひとつ中国ならではなのが、冬の寒い時期になるとズボンは2枚重ねて履かせることです。内側に薄いズボンと、その上に綿の入った厚いズボンを重ねて履かせます。暖かそうですが、暑くないかな?と心配になることがあります。
最近では厚着させるのもよくないと認識する人もいますが、やはり小さい子がモコモコとたくさん着込んでいる姿を見かけることが多いです。
ベビーカーはたたまない
中国の街中で子どもを連れているとよく知らない人から声をかけられます。かわいいね、とか何歳?と声をかけられておしゃべりに発展することは日常茶飯事です。
子どもと一緒に地下鉄やバスに乗ると必ず誰かが席を譲ってくれます。どれだけ離れたところからでも、声をかけてくれるのです。見て見ぬふりをすることは決してありません。子連れだけでなくお年寄りにも席を譲るのは当然で、中国の人はそういう習慣が身についています。
また、ベビーカーをたたまずにバスや電車に乗っていても誰一人として迷惑そうな顔をしません。階段の上り下り、乗車、降車の際には必ず誰かが手を差し伸べてくれます。
空港のイミグレーションや、公共機関でも、当たり前のように子供、お年寄りを優先してくれて、何十分も並んでいる列でも比較的優先して対応してくれます。
中国の地下鉄やバスは少し運転が荒いときがあり、子連れで立ったままというのはとても危険なので満車の中でも席を譲ってもらえるのはとても助かります。
いかがだったでしょうか?まだまだ例を挙げればキリがありませんが、隣国の文化でさえもこれだけの違いがあります。マーケティングの観点から見ても、どれだけ現地の文化を理解し、寄り添っていけるかがとても大切になっていきます。
弊社では文化理解のその先、文化の差を理解し、チューニングすることを『カルチャライズ』と呼んでいます。
そちらは当社総経理 久保山と、董事 川崎の共同著書「ブランドカルチャライズ」にて詳しくご紹介していますので、気になった方は是非これを機に手に取ってみてください。あなたに新たな気づきと意外なヒントを与えてくれる一冊になるかも知れません。是非お気軽にご連絡頂ければ幸いです。