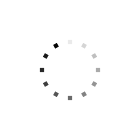ギザギザ歯キャラクター、Labubuのリベンジ:「ブサキャラ」から大人気トイへと変貌を遂げた理由とは?
2024年7月、バンコクのスワンナプーム国際空港には、まるで夢のような光景が繰り広げられました。数百人のファンがペンライトを掲げ、歓声を上げながら到着ゲートを取り囲んでいました。ファンの出迎えを受けるのは、なんと身長20cmにも満たないぬいぐるみ「Labubu(ラブブ)」です。
タイの観光スポーツ大臣は自ら花輪をLabubuにかけ、「Amazing Thailandアンバサダー」の称号まで授与するというVIP待遇。この中国発のおもちゃブランド「POP MART(ポップマート)」が生み出したこの小さな妖精は、スター並みの歓迎を受けました。

Labubuの誕生は、まるでアートの実験のようなものでした。2015年、香港のアーティスト龍家昇氏が北欧神話からインスピレーションを受け、9本の歯と尖った耳を持つ森の小妖精「Labubu」を生み出しました。Labubuは「内面は善良だけれどイタズラ好き」というキャラクター設定で、当初はアート展から派生したグッズでした。2019年にポップマートとライセンス契約を締結後、本格的に商業市場へ進出しましたが、当時のLabubuの人気は今ひとつでした。2023年、Labubuが属する「THE MONSTERS」シリーズの売上はポップマート全体の5.8%にとどまり、主力の「MOLLY」シリーズに比べると存在感は薄いものでした。

画像出典:https://www.163.com/dy/article/JUI0BJCE0512830U.html
そんなLabubuに2024年4月、転機が訪れました。韓国の人気ガールズグループ、BLACKPINKのLISAがSNSで複数のLabubu人形を投稿すると、東南アジアのファン達の間で人気が一気に加熱。 さらに、タイのシリワンナワリーナー王女がパリのファッションウィークに出席した際、HERMÈSのバッグにLabubuのチャームをつけていたのをきっかけに、浜崎あゆみやリアーナなど世界のセレブたちも続々とLabubuを身につけるように。この尖ったギザギザ歯の妖精は、いつの間にか世界的ファッションアイコン達の「定番アクセサリー」になったのです。

右:タイ王女がパリ・ファッションウィークにLabubuチャームを携えて登場。
画像出典:https://news.qq.com/rain/a/20241203A06AXM00
10年かけて磨き上げた、ちょっと不気味なキャラクター
Labubuの誕生はとてもドラマチックなものでした。2015年に香港のアーティスト龍家昇氏は、善と悪が交錯するヨーロッパの幻想文学に登場する精霊たちからインスピレーションを得て、絵本『精霊三部作』の中でLabubuという“いたずら好きのモンスター”を生み出しました。当初のLabubuはソフビとしてアート展で発売されましたが、「かわいくない」と不評でした。しかし2018年のポップマートとの契約を機に状況が一変し、口を大きく開けて尖った歯を見せるこの精霊は、ようやく脚光を浴び始めます。
ポップマートは、Z世代の「ギャップ萌え」の価値観をうまく捉えたものでした。鋭い牙と無垢な瞳、ダークファンタジー的な森とふわふわ素材のぬいぐるみ、といったギャップ。「ちょっと不気味、だけどなんだか愛おしい」存在は、若者たちの“個性を表現したい”という欲求にぴたりとハマったのです。そして2024年、韓国ガールズグループBLACKPINK のLISAとLabubuの“夢の共演”がすべてを変えました。LISAがInstagramでLabubuのチャームを投稿した瞬間、東南アジア市場での売上が一気に300%アップ。Labubuは一夜にして大ブレークを果たしたのです。
「ただのおもちゃ」から「ステータス」への進化
Labubuの世界的なブームは、すでに社会現象レベルとなっています。2025年4月、第3世代のぬいぐるみシリーズ「前方高能(=この先、衝撃あり)」が発売された当日、ポップマートの公式アプリは米国App Storeのショッピングカテゴリで1位にランクインし、シカゴ店舗の前には寝袋を持参して徹夜で並ぶファンまで現れました。中古市場では、定価99元(約2,000円)の通常モデルに対して10〜200%のプレミアムがつき、レアモデルは2,300元(約4.5万円)するものもあり、「塑料茅台(プラスチックのマオタイ酒)」という呼び名がつけられたのも納得の加熱ぶりです。その勢いは世界各地に波及し、バンコクのポップアップショップは初日だけで1,000万元(約2億円)を売り上げ、ロンドンのハロッズ百貨店ではLabubuとHERMÈSバッグを交換するという、まさかの取引まで行われ話題となりました。
さらに驚くべきはLabubuの“ジャンルの壁を超える力”です。ルーヴル美術館とのコラボで生まれた「モナリザLabubu」は、パリ観光のお土産定番となり、茅台(マオタイ)との干支酒コラボは72秒で完売。Web3の世界ではミームコイン「Labubu」が登場し、時価総額は一時4,900万ドル(約76億円)に到達しました。
さらにTikTokでは「#StylingMyBagwithLabubu」のハッシュタグが再生数10億回を突破。若者たちはハイブランドのバッグにLabubuチャームをつけ、“着るアート”、“持ち歩く個性”としてトレンドを楽しんでいます。
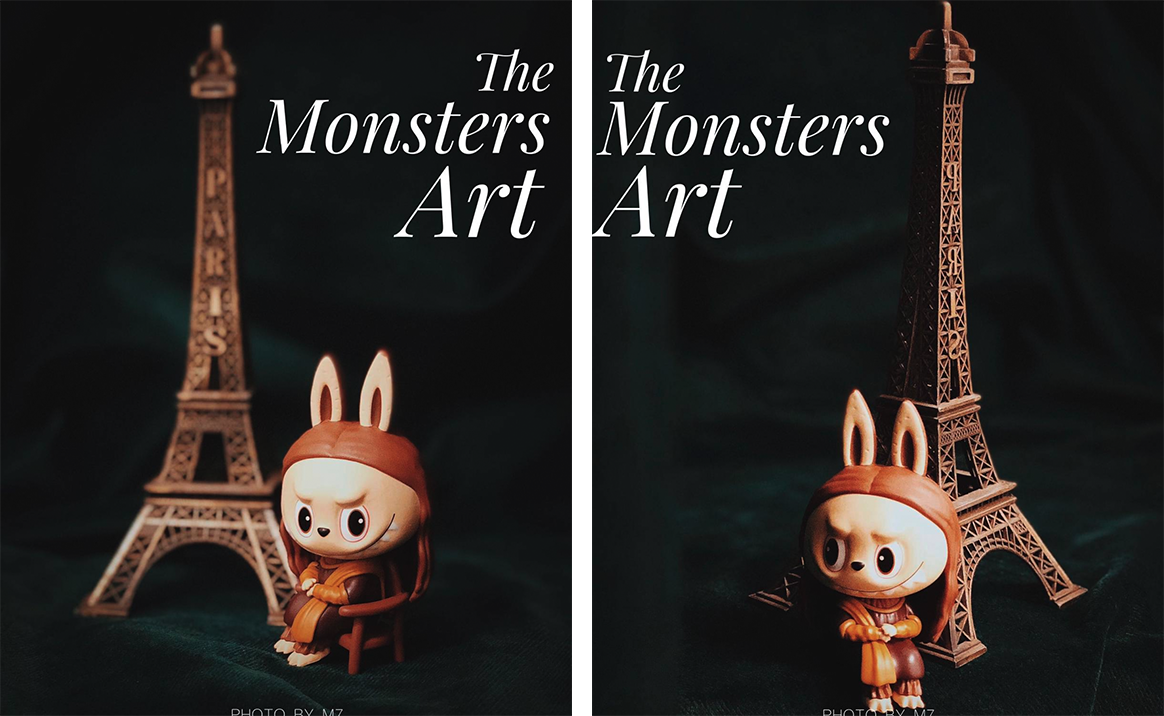
画像出典:https://post.55haitao.com/show/109232/
実体からデジタルへ、「メタバース」のその先へ
Labubuの未来は、もはや物理的な枠を超えています。ポップマートはLabubuを主人公にしたアニメーション短編の制作を発表し、「妖精アイドルグループ」の世界観構築を進めています。Web3領域では、Solanaチェーンと連携したブロックチェーン上の“ブラインドボックス(ガチャ)”がテスト段階に入り、ユーザーはトークンのステーキングを通じて、隠しアイテムの抽選に参加できる仕組みです。これにより「デジタル資産」と「現実世界の権利」のシームレスな連携が可能になりました。こうした“リアルとバーチャルの共生”戦略によって、Labubuはただのトイから「デジタルネイティブ」へと進化。NFTシリーズのOpenSeaでの累計取引額は、すでに2,000万ドル(約31億円)を突破しています。
Labubuのグローバル展開も加速中です。ポップマートは2025年に海外で新たに100店舗の新設を予定しており、北米市場の売上は2020年当時のグループ全体の収益水準に匹敵する規模に達する見込みです。また東京の原宿やパリのシャンゼリゼ通りといった世界的なファッショントレンドの中心地では、Labubuのテーマストアが新たな「映えスポット」として注目され始めています。JPモルガンは最新レポートで「LabubuはHello Kittyに匹敵するポテンシャルを秘めており、中国発のグローバルIPになるだろう」と分析しています。
Labubuの成功事例が示す、新時代の消費ロジック
1.「かわいい神話」をひっくり返す:Labubuは「かわいい=正義」という固定観念を壊し、「ブサかわ」という新しい美意識を提示。あるREDユーザーは「Labubuのいたずら顔は、完璧主義への反抗。誰もが美しさを追い求める時代に、不完全さを受け入れる勇気をくれた」と投稿しています。
2.情緒の補償:個人化が進んだ社会において、Labubuは若者たちの「心のパートナー」となっています。60%以上の購入者がLabubuの「日常写真」を撮影し、34%が毎月Labubuのコスチュームを買って着せ替えるなど、こうした「育成型消費」は失われつつある情緒的なつながりを再構築しようとする試みなのです。
3.ガチャの中毒性:レアアイテムの排出率0.69%という絶妙な設計がコレクター心理を刺激。「開封→SNS投稿→転売」という流れがSNSと中古市場で完結するサイクルを形成し、ポップマートは希少性を武器に熱狂を巻き起こしました。一方で、イギリス店舗での買い占めトラブルや、再入荷通知が機能していないとの苦情など、転売対策や供給管理の課題も表面化しています。
4.グローバル×ローカル:タイでは寺院限定モデル、北米では「アジアンカルチャー」をテーマにしたシリーズを展開するなど、ポップマートは「グローバルな物語+ローカルな表現」を巧みに組み合わせて文化の壁を乗り越えています。例えば、日本ではLabubuが仏具風にアレンジされ、「金運アップのお守り」という形で展開されています。
Labubu現象がブランドに与える3つの示唆
1.IPの人格化:キャラクターに明確な個性と成長ストーリーを持たせることで、消費者の感情の投影を促しています。Labubuが「おもちゃ」から「パートナー」へと変化するプロセスは、まさに「優れたIPは生命体である」ことを示しています。
2.テクノロジーの活用:Web3やメタバースは単なる流行語ではなく、IPの資産価値を最大化する新たな戦場です。Labubuコインの大成功は、文化的アイコンとブロックチェーンとの融合が、物理的な境界を超えた価値を生み出せることを証明しました。
3.「希少性」と「供給」のバランス:希少性を演出しながら、安定供給も確保するには繊細な舵取りが求められます。ポップマートは「地域在庫+動的補充システム」により物流効率を改善していますが、転売対策やブランド信頼性の維持は依然として大きな課題です。
最後に
“ブサかわ妖精”Labubuが世界中で愛されるようになったのは、若者たちの「自己表現」「つながりを求める気持ち」「コレクター心理」を的確に押さえていたからです。そこに、スターの起用、SNSでのバズ、ガチャの中毒性、地域ごとのローカル展開といった複数の仕掛けが掛け合わさり、「ちょっと好き」だったはずの存在が、いつの間にか「手放せない存在」になっていきました。
この現象が教えてくれるのは、本当に“楽しい”と感じ、“共感”できるものにこそ、人は時間もお金も惜しまずに注ぐという、現代社会の消費の本質なのです。