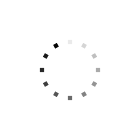ブランド管理のプロトコルを合わせよう
balconia Shanghai総経理の久保山です。今日はブランド戦略のお話です。
戦略の仕事をしていてやっぱり難しいなと思うのが戦略の落とし込みです。マーケティング活動は多くの部署で成り立っているので、各チームに戦略を理解して実施してもらわないといけないのですがなかなかうまくいかないですよね。「コンサル入れても結局実現性のない絵に描いた餅なんだよなー」というぼやきをよく聞くんですけど、それもおそらく落とし込みの難しさを指摘しているのだと思います。実際コンサルの立場で入っていて難しいのはそういうフェイズだったりします。
このアジェンダってけっこう体力のいる分野で、多くのノウハウが必要なのですけど、その中でぜひひとつご紹介したいのが「プロトコルの統一」です。
プロトコルってなに?
プロトコルの原義をぐぐってみると、
the system of rules and acceptable behaviour used at official ceremonies and occasions
となっています。直訳したら変な日本語になっちゃったので、ざっくり訳でいくと、「公式の儀式などで使われる、受け止め可能なルールシステム」みたいなことですね。
ブランド戦略を書いてる人々は、やはり他の部署に比べてマーケティングのことよくわかってる方が多いですし、リサーチを行なったり、競合の動向もベンチマークして、ファクトもたくさん持っています。
他方で、宣伝や営業など関連する部署は別の専門性を持った組織で、情報にも格差がありますから、彼らにも受け止められるルールシステムが必要だ、ということなんです。
特にマーケティングドリブンの会社は共通言語となるマーケティングの考えかたが確立されているのでそんなことやんなくていいんですけど、営業ドリブン、研究開発ドリブンなど、別のチームを中心に発展してきた組織ではマーケティングの共通言語がない、ということがまま起こっていたりします。
そこで、出てくるのがプロトコルの統一、というわけです。
戦略相関図
プロトコルの統一で作るのをおすすめしているアウトプットが戦略相関図です。
例えばブランドマネジメントチームが作ったブランド戦略。そう題されるPPTの中身は「ブランド・エクイティ」「ターゲット戦略」「アイテム戦略」などが入っている。
宣伝部が作ったコミュニケーション戦略。そう題されるPPTには「ターゲット戦略」「クリエイティブ戦略」「メディア戦略」などが入っている。
営業部が作ったチャネル戦略。そう題されるPPTには「ターゲット戦略」「出店計画」「チャネル別の展開SKU」などが入っている。
あれ、でも、よく見ると宣伝部のターゲットとブランドマネジメントチームが書いたターゲット微妙に違くない? あれ、営業部がやろうとしてるのブランド・エクイティ育成してなくない?
みたいなことありませんか?
これは戦略同士の相関関係や意味合いが各部門で統一されていないということです。
このため、戦略そのものではなくて、戦略同士がどのような関係性にあるのかを定義した全体像のようなもの(=戦略相関図)がやはり必要になる、ということで、そこに一貫性を担保し運用していくのがブランドマネジメントのお仕事、という考えかたです。
戦略に一貫性をもたせよう、ということ自体はどの部署も結構支持してくれる考えかたなので、相関図を作って意味合いを確認する、ということにはどこからも抵抗が起きないことが多いです。そうしてどんなプロトコルで議論するかを統一した次のステップで、戦略を落とそうとすると
「え、ってことはブランドマネジメントチームの戦略に従うと○○は広告費かけなくていいってこと!?△△チャネルではシニアが最も買ってるのこの製品なんですけど!顧客離れますよ!」
みたいな議論が起き、はじめて戦略を自分ごととして受け止めてもらえ、理解も深まります。こうした関連性を示さないと他人事の戦略なんですよね。
落とし込み問題に悩まれてるブランドマネージャーは一度これまでに全部署が経営に提示している戦略資料たちに目を通してみると良いですよ。この問題にハマってるケースけっこうよく見ます。
そして私見ですけどよく外資の敏腕マーケターとかが日本企業のCMOとかなるとこの辺の改革から着手してる印象あります。
久保山