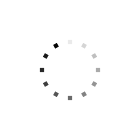中国エンタメ「宮闘劇」を知っていますか?
balconia上海副総経理の川崎です。今回は趣向を変えて、中国エンタメについて書いてみます。
突然ですが問題です。以下の中国語を聞いたことがありますか?
①哀家(アイジャー) ②朕(ジェン) ③臣妾(チェンチエ)
これらの言葉が頻出する場と言えば、そう、中国ドラマの1ジャンルである「宮闘劇(宫斗剧:ゴンドウジュウ)」です。
宮闘劇とは、皇帝の後宮(日本で言う大奥)を舞台に繰り広げられる女性達の闘いを描いたドラマのことを指します。
実はこの宮闘劇、2019年に当局より「熾烈な争いの様が社会に悪影響を与える」として取り締まり対象となり、過去のほとんどの主要作品が中国国内では見ることが出来なくなった上に、新しい大型作品も生まれていません。(え?!規制?と思われるかもしれませんが、実際にそのくらい熾烈な闘いが描かれてはいます)
そんなもんをわざわざ紹介してどうする・・・?という大いなる疑念を抱きつつ書き始めたところ、なんと最近多くの作品が一部内容を修正した上で改めて公開されていることに気づきました。
また、Youtubeやアマゾンプライム等で、日本から見れる作品も多々あります。
ということで、今回は宮闘劇を見るとこんな良いことあるよ、ということを書いていきたいと思います。
※上記の問題①~③いずれも自分自身を呼ぶ言葉、つまり「私」の意味です。①は太后が、②は皇帝が、③は妃が皇帝に対して自分を呼ぶ際に使われます。(あくまでもよくある宮闘劇の中の話なので正確なことは各自調べてみてください。)
中国人みんなが知る「ネタ」の宮闘劇
宮闘劇をわざわざご紹介する理由ですが、その1つは以下の図を見て下さい。
中国に住んでいる(もしくは、過去住んでいた)方は、一度はWechatのスタンプや各種動画で見たことがあると思います。

これは宮闘劇の代表作「甄嬛传(ジェンフアンジュアン)」のシーンを抜き出したものです。2011年の作品ですが、いまだに多くのメディアで取り上げられます。
中でも、主人公である甄嬛(上記図の真ん中)を差し置いて、悪役にあたるライバルの華妃(図の右端)は、その大袈裟な表情や、分かりやすい悪役ぶりから色んなところでパロディもされていますし、イラっとさせる表情の代名詞にもなっています。
つまり、代表的な宮闘劇は、中国人との会話で何かと出てくるネタとして、知っていて損はありません。
中国語の聞き流しにぴったりの宮闘劇
宮闘劇をご紹介する理由のもう1つは、中国語や中国文化の学習として、見流し・聞き流しにちょうど良いと感じるからです。
代表作はだいたい80話、長くて100話前後と、笑うしかない位のボリュームなので見るのに相当な覚悟が必要となりますが、逆に時間をつぶすのにはもってこいと言えます。ロックダウンの2か月間も、宮闘劇を見始めてから高速で過ぎていった感がありました…。
宮闘劇は、日本の時代劇のようなものなので、劇中で使われる言葉に聞き慣れないものも多く、固有名詞もちょくちょく出てくるので、はじめは取っつきにくいかもしれません。
ただし、ある意味では、テーマや話の展開は非常に明瞭なので「見流し・聞き流し」に実はぴったりじゃないかと考えています。中国語のリスニングを鍛えつつ、中国人共通のネタを把握し、中国の文化も知ることが出来る、結構お得なものだと言えそうです。
宮闘劇のテーマとは?
先述の通り、宮闘劇とは、中国の後宮を舞台に繰り広げられる女性(妃)達の闘いを描いたドラマです。基本、テーマはそれだけなのです。
では何のために妃たちが闘っているのかと言うと、まずは皇帝に気に入られて位を高めていくこと。そして究極的には皇帝の後継ぎを生んで、自分の子どもを皇帝に、そして自分自身が太后として君臨することが最終ゴールです。
だいたい80話、100話とかなりの長いエピソードがありますが、基本行われることは上記のゴールに向けての足の引っ張り合いと騙し合いです。色々並行して話が展開されますが、基本はこれを延々と繰り返しているだけ、と言えばそれだけです。
それを前提に考えると、色々難しそうなことが語られたり、たくさん登場人物が出て来ますが、一つ一つを理解する必要はほぼなく、「あー、この人が今味方か」「あー、今のメインの敵はこの人か」くらいの理解さえ出来ていれば大筋の把握に支障はありません。
そのため、一見難解そうに見えて、何も難しいことを考えず、ぼーっと見流す、聞き流すのに実はぴったりなのが宮闘劇なんじゃないかと考えています。場面展開も分かりやすいので、見ていても退屈にはならないと思います。(少なくとも前半は・・・)
取っつきやすいように、典型的なキャラクターもご紹介しておきます。キャラ設定も、どの作品でもそこまで大きな違いはありません。
• 血筋のハンデをものともせずに実力であれよあれよと出世していく、ザ・成り上がりの主人公。
• いや、それ本気で言ってる?の連続、ザ・ふしあな、皇帝。
• 自分で負けフラグを立ててまわる、ザ・悪役、美人妃。
• やさしい顔して実はえげつない、ザ・腹黒、先輩妃。
• けっきょく何でもお見通しのザ・ラスボス、太后。
と、思わず「ザ」を付けてしまうくらい、それこそかつての少女漫画や昼ドラを想起させるような分かりやすいキャラクター達で溢れています。
どうでしょうか?こうやって見ると魅力的に見えて来ましたか?
作品の中には、同時代を別の妃の視点から描いた作品もあり、他の作品では普通に良い人だったのに、別の作品だとザ・悪役になってる、といったオーバーラップも面白いポイントです。
宮闘劇の代表作
古いものから新しいものまで多くの作品がありますが、何から見るか、と言えばやはり先ほどあげた「甄嬛传(ジェンフアンジュアン)」がおススメです。
Youtubeにも公式でアップされているようですし、アマゾンプライムで「宮廷の諍い女」という和訳タイトルで公開されているようです。

この作品が最近の宮闘劇の流れを作ったと言われますし、中国においても認知度がずば抜けて高いです。もし分からない箇所等があれば周りの中国人の方に聞けば、おそらく「あー、あのシーンね。あれは・・・」と解説してくれることでしょう。
その他にも、ファン・ビンビンが国民的女優として知れ渡るきっかけとなった『武媚娘传奇(日本公開版は「武則天-The Empress」)』、宮闘劇なのに「闘わない妃」を描いて話題となった『如懿传(日本公開版は「如懿伝~紫禁城に散る宿命の王妃~」)』なども有名です。
なお、頑張って古い作品から見ようというガッツのある方もいるかもしれません。私もそんなにたくさん見ているわけではありませんが、個人的には甄嬛传以降の方がお話的にも、視覚的にも見やすいと感じますので、興味を持たれた方は最近のものを見るのをおススメします。

宮闘劇で知る中国
ここまで、取っつきやすいようにやや極端な説明を続けて来ましたが、好きになれば深い味わい方が出来るのも宮闘劇の魅力です。
当時の風習・習慣を知るだけでも面白いですし、それぞれのキャラクターの策略が錯綜する様子は見ごたえがあります。後宮で権力を掴むために、一族、つまり「氏」の力を利用しているように見えて、逆に「氏」に利用され、それでも「氏」のために自己犠牲に身を投じる妃たちの姿は、ぱっと見はただの足の引っ張り合いに見えて、実は深いものがあります。
また、宮闘劇を見ていると、中国人の伝統的なメンツ文化とはどういう文脈なのか、中国の方が心を動かされるエピソードや表現とはどんな世界観なのか等、現代の中国を理解するのにも役立つことは少なくないと思います。
中でも、劇中で描かれる「女性像」は、社会トレンドの影響も見られるため興味深いポイントです。
宮闘劇に出てくる女性達はいずれも強烈な個性をもっていますが、共通して強い女性が描かれています。特に主人公は、様々な資源を利用しながら、自らの知恵と実力でのし上がっていきます。
甄嬛传が大ヒットした2011年。開放政策によって中国の社会経済が急速に発展を続けたタイミングと重なりますが、その中で自立し、自身の能力・実力によってステップアップしていく主人公 甄嬛と自分自身を重ね合わせた女性も少なくないでしょう。
2018年の如懿传の主人公 如懿は、皇帝と少なくとも2人の間の関係性においてはカップルとして対等な立場を求めます。そのような態度、考え方はこれまでの宮闘劇の主人公像とは少し異なるものであり、今の時代だからこそ共感を生んだキャラクターとも言えるかもしれません。
宮闘劇を通して中国語だけでなく、中国文化への学びを深めるきっかけになると思います。
以上、ざーーーっと宮闘劇をご紹介してきました。
皆様も是非、中国エンタメに触れてみてください!
こんな記事もよく読まれています
-
TikTokやWechatなど多くのSNSで新たなトレンドに関するトピックがよくあがっていますが、その中でもよ […]
2022.06.20 Kaki中国における「メタバース」と「マーダーミステリー」の考察 -
balconia上海副総経理の川崎です。今回は、中国の消費者を理解する上で大事となる社会的なトレンドのお話です […]
2020.11.04 KAWASAKI中国マーケットのキーワード:「做自己」自分らしく -
川崎です。前回転職してきました、と紹介させて頂いたばかりなのですが、同じようなタイミングで中国人の友人の家具屋 […]
2020.06.12 KAWASAKI家具屋で実践!中国ブランドマーケ