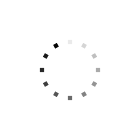ただの2ステージゲームなのに…
最近のホットな話題といえば、突然バズったウィチャットゲーム「羊了个羊」です。どこに行っても、「羊ゲームやった?」というフレーズは必ずと言っていいほど耳に入ってきます。
これは9月に出現した、同じ画像が3つそろえば消える系の「3パズルゲーム」です。全ての画像が消えたらゲームクリアですが、とりわけ不思議なのは、このゲームにはわずか2ステージしかないのに、人々を大いに熱狂させているところです。
私もゲームをシェアしてもらったので早速やってみました。最初は自信満々でしたが、最後はゲームクリアできずにブチギレてしまいました。。
実は、このゲームのステージ1ではプレイヤーに慣れてもらうため、簡単にクリアできるように設計されておりますが、ステージ2になると急に難易度が跳ね上がります。このギャップこそが人々のチャレンジ精神を奮い起こしているのです。

さて、こちらのデータを見てみましょう。「羊了个羊」ミニアプリデータによると、9月13日に550万のユーザーがゲームにチャレンジしており、9月14日には2600万ものユーザーが「今日のチャレンジ」に参加していました。そして、ウェイボーでは、ハッシュタグトピック「羊了个羊のクリア率は0.1%以下」の9月15日の閲覧回数は3399.4万にも上っています。ハッシュタグトピック「夢の中でステージ2をクリアした」等も検索急上昇ランキングにランクインしました。


「羊了个羊」はなぜこれほどまでに人気爆発したのでしょうか。実は、ミニゲームに使用されている小道具も大きな役割を果たしているのです。例えば、「やり直し」や「復活」といったツールを使いたければ、広告を見るか、お友達にシェアしなければなりません。これはまさに「拼多多」のゲームバージョンだと言う人もいます。なぜなら、この戦略は「拼多多」の「値引き」アルゴリズムに酷似しており、ユーザーのシェア欲が掻き立てられているからです。また、ウィチャットを媒体としているため社交属性を持っており、膨大なユーザーを確保しています。アプリ開発にもそれほど手間がかからず、簡単にシェアできるなどといった特性によって、効率よく拡散されたのでしょう。その上、周辺グッズや表情スタンプがすでに発売されているようで、本当に目を張るようなスピードです。

こんなにもシンプルなのに、一体何が人々を熱中させているのでしょうか。ユーザー心理の観点から以下4点が考えられます。
ゲーム中毒原因その一:「慣性認識によるミスリード」
なぜなら、このようなゲーム設計は傲慢さと自信過剰な人間心理を掻き立てられるからです。ステージ1は簡単にクリアできるので、まずは満足感をたっぷり与え、ゲームルールに馴染んでもらいます。すると、人間は心も脳も「ステージ2もクリアできる」というようにいつもの回路で自動思考してしまいがちです。同様の手口はかの有名な「ポンジスキーム」でも使われています。
ゲーム中毒原因その2:「名誉感を育む」
人間は群れで生きる動物であり、携帯電話の世界でも変わらず、グループに群れています。「羊了个羊」のステージ2では、ゲームクリアが出来なかった場合にランキングが表示されます。しかし、これはユーザー自身の順位ではなく、所属する都市のランキングです。このとき初めて、自分がクリアできなかったことで都市全体の足を引っ張ったのではないかということにはっと気づくのです。自分の所属する都市に対する責任感から、再トライすると人も少なくないはずです。
ゲーム中毒原因その3:「ここまで来たことだし」
「ここまで来たことだし」という慣用句の後半をご存知でしょうか。「やれるだけやってみる、絶対に諦めない」です。つまり、何かを始めた以上、途中で困難があっても、成し遂げるには多少の努力が必要だと認識するのです。普通の人なら、ここまで頑張ったのだから、中途半端なことが嫌なので続けるしかないでしょう。
そして4つ目の中毒原因は、「自分こそがその0.01%」という人間心理です
ゲームをシェアする際のキャッチコピーもあざとく、心に刺さるものばかりです。「0.01%の人しかクリアできないらしい!傷つきやすい人はご遠慮ください!」、「知能指数が低ければ、チャレンジしないほうがいい!」などがあります。どうでしょうか。これは侮辱としか思えない、負けず嫌いな方なら「わたしはクリアできるかも、やってみよう!」と煽られて、思わず勝負してみたくなるかもしれません。

クリエイティブの仕事を長くしていると、自動思考モードに陥りがちです。上述したステージ1をクリアしたときみたいにいい気になっていると、ステージ2で奈落の底に落とされる羽目になってしまいます。
こういう時こそ、私たちは「羊了个羊」の「負けないぞ」精神を見習うべきです。良いクリエイティブを創り出せる人間は世の中に0.01%しかいないと自分に言い聞かせ、自分こそがその0.01%なのかもしれません。